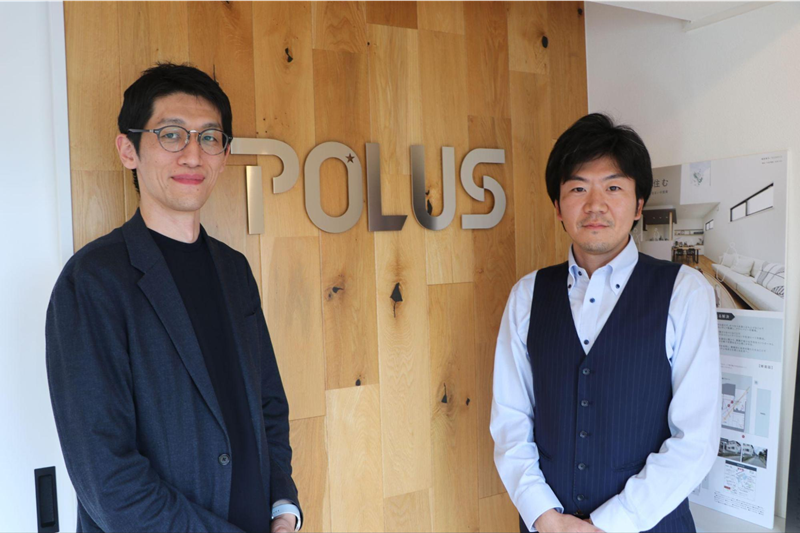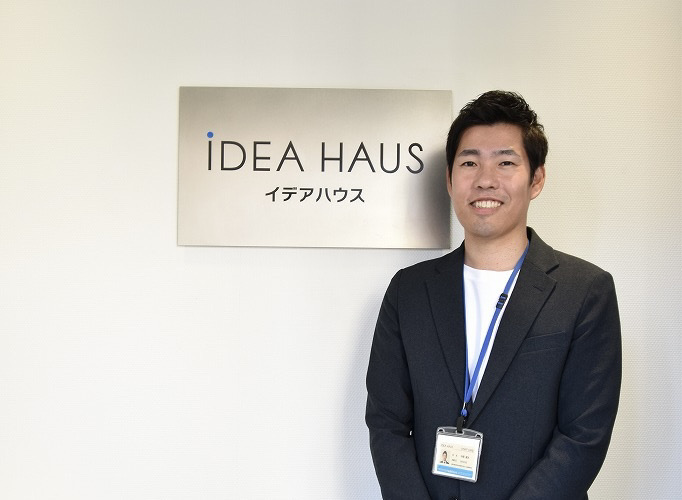【株式会社中央住宅(ポラスグループ)】導入半年で成約!業務効率化と顧客ニーズに無人内見が効果を発揮!
中央住宅株式会社 不動産開発部 企画開発課 課長 村田嵩胤さん
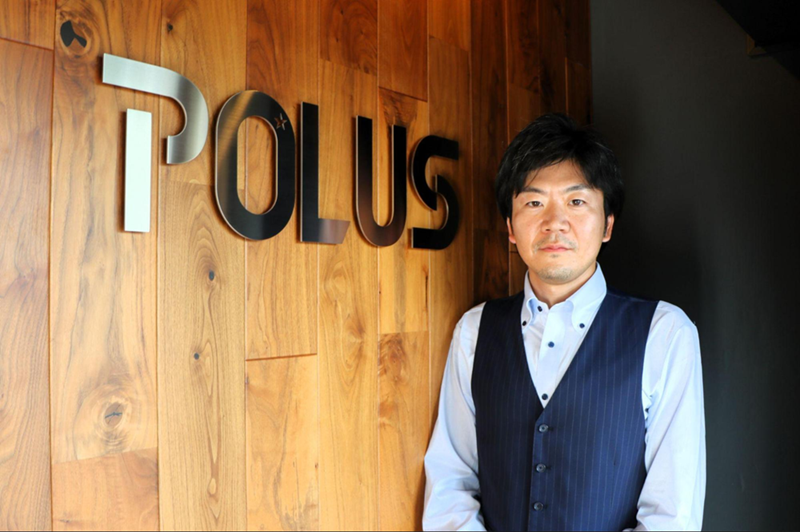
株式会社中央住宅(越谷市)不動産ソリューション事業部 不動産開発部 企画開発課 村田俊郎さん
「無人内見くん」を導入いただいている企業にサービス導入に至った経緯や、導入の効果をインタビューさせていただきました。
今回は、株式会社中央住宅(越谷市)不動産ソリューション事業部 不動産開発課 課長の村田俊郎さんに話を聞きました。
ポイント
導入情報 ※2024年10月時点
ポラスグループの株式会社中央住宅は、埼玉県を中心に東京都北部、千葉県の一部地域で不動産事業を展開する総合不動産会社です。
ポラスグループ全体で年間約4,000戸の住宅を供給しています。「責任一貫体制」にこだわり、担当者一人ひとりが顧客に密着したサービスを提供しています。
業務効率化や多様化する顧客ニーズへの対応課題
サービスを導入する前に、どのような課題を感じていましたか?
村田課長:従業員の働き方改革や業務時間の見直しがあり、効率的な営業活動や業務負担の削減といった課題がありました。現在は、夜8時になるとパソコンが強制的にシャットダウンされるという徹底ぶりです。いかに成果を出すか、効率的に働けないかと考えていました。
また、定休日は顧客対応ができません。平日が休みのお客様もいらっしゃいます。そういった方たちからの反響や現地案内でできないといった部分も頭を悩ませていました。
加えて、時代の変化によって物件購入者の半数以上が共働きの方になったことで、より多様な接客や案内が必要になっています。現場の営業担当の話を聞いていると、例えば平日の遅い時間に物件を見たいニーズや、夫婦別々に物件見学されるといったことも多かった。これに営業担当が毎回同行するのは、かなり難しい状況でした。
働き方改革による勤務時間の制限と、お客様の生活スタイルの変化が大きな課題だったんですね。
村田課長:お子さんがいるご家族でも、意外と土日は習い事やイベントなどで忙しい。そういう方は、夜遅くに見学に来たりするんですよ。そういうニーズにも対応しないといけないと感じていました。

導入半年で成約。月間の内見予約件数も増加傾向
具体的に「無人内見くん」をどのように活用していただいていますか。
村田課長:モデルハウスにIoT機器をセッティングして無人内見の環境を作り、HPに内見予約のフォームを設置して、集客源の1つとして活用しています。
今まで、ホームページでの集客といえば資料請求とか来場予約の2パターンしかありませんでした。大半が資料請求の問い合わせです。当然資料を送るんですけど、その後に繋がらないことが結構多いんですよ。一方で、来場予約の顧客は具体的に動いている方です。「無人内見くん」はちょうどその中間の方たちと接点を持つことができると感じています。
資料請求だけじゃ物足りなくて、実際に物件を見てみたい。しかし、営業担当者に接客してもらうほどではない。
資料請求だけじゃ物足りなくて、実際に物件を見てみたい。しかし、営業担当者に接客してもらうほどではない。 内見予約の際には、きちんと免許証をスマホで撮影しなければならないので、セキュリティ的にも安心で、またわざわざ身分証明をしなければならないので、顧客も中途半端な気持ちでは内見予約しません。
ありがとうございます。「無人内見くん」によって具体的に、成果に結びついていますか?
村田課長:2023年8月から導入して、半年で1件成約が出ました。
年末の正月休みの間に、ご夫婦が見学され、年始早々に親御さんと一緒に再度無人で内見された後に購入されました。まさに、最初から最後まで無人内見で決まった事例です。
現在は、4つの現場で導入していて、1カ月で15件前後の来場があります。導入当初は来場数が伸び悩んでいたんですが、プロモーションの工夫や、ランディングページの作成などのアドバイスをいただき、徐々に予約件数も増えています。これは非常に大きな成果だと感じています。
営業担当の方々の反応はいかがですか?
村田課長:うまく活用している担当者が増えてきました。「ちょっと見に行きたいんだけど」とか、「この時間帯に見に行きたいんですけど」といった要望に自分が対応できないとき、どうぞ無人内見を予約してくださいと案内しています。
また、「無人内見くん」にはスマートロックも備わっているので、内見予約されていないお客様が、飛び込みで現地に来られたときも、遠隔で開場できたりするのは凄く便利ですよね。
内見だけでなく、顧客対応にも活用いただいているんですね。その他にも効果はありましたか?
村田課長:遠方から物件を見に来るお客様の行動パターンが分かってきたことですね。例えば、埼玉県や千葉県など東京近郊の物件を購入されるのは、都内に住まれている方が多いのですが、どうやら事前に下見に来られているようなんです。
どういった街並みなのか、どういった雰囲気なのか。営業担当者がいたら、いいことしか言わなさそうだし、自分の目で確かめたい。そう考えるお客様が増えているなかでは、無人で内見できることは、お客様にとってもメリットがあるんじゃないかなと思います。
また、同じ方が複数の物件を見に来ているといったデータも取れて面白いですね。これって、「無人見学くん」があるからこそできることだと思うんです。
現地に看板を設置しており、QRコードを読み込んで、その場で無人内見の予約を取っていただくケースも多く、飛び込みのお客様に物件を見てもらえることも増えています。
導入を決めた際、セキュリティ面での懸念はなかったのでしょうか?
村田課長:もちろん最初は懸念がありました。変な人が入ってきちゃう可能性とか、イタズラされたりといった心配ですね。でも、結果論から言うと何もなくて、トラブルも1度もありません。
やはり、予約の際に身分証明を撮影して登録しなければならないというのが大きいと思います。また、物件に設置したスマートカメラが録画しているという点も安心ですね。予約時間になると、エアコンや証明などが自動で作動するようになっているので、お客様も空き家を見に来ている感覚ではないと思います。
内見データを企画や営業研修に活用
当社(ショウタイム24)への要望はありますか?
村田課長:あえて言うのであれば、現地に来られたお客様が物件を見て話されている声をきちんと拾えるように、さらに感度の高いマイクがあれば良いと思っています。
お客様の「ここいいよね」とか、「これいらなくない?」といった、生の声をもっと聞けたら、企画に活かしたり、営業社員の勉強資料にも使えたりできるのではないかと考えています。
なるほど。
村田課長:音声は、無人内見だけの場面だけでなく、エース社員が物件案内時にどういった提案をしているのか、といった様子を社員教育などにも活用できると思っています。ロールプレイングではなくて、生のお客さんとの接客の様子が分かる。
逆に、新人の接客の様子を沿革で上司が見て、リアルタイムに指示を出すことなどもできるかもしれません。そうすれば提案確度も上がっていきますから。
顧客の変化に対応し、住まいの道しるべを提供する
顧客の変化や、業界に感じる課題はありますか。
村田課長:最近の傾向として、不動産投資的な考え方で家を買う人が増えてきていると感じます。例えば、若い方々は、資産価値の落ちない物件だと判断すれば50年などの長期ローンを組んで購入されます。
50年って普通に考えるとびっくりしますよね。でも、彼らの考え方を聞いてみると、月々の返済価格を下げると9000万円弱の物件でも月々の返済額は15万円程度で済みます。そして、しばらく住んで価格が上昇しないまでも、落ちないのであれば、住み替えて次の住まいにステップアップしていく。納得ですよね。
マイホームが終の棲家といった感覚ではなく、不動産投資のような感覚で資産性などを気にしている顧客が増えているように思います。
そういった顧客の変化に対して、不動産業界はどう対応すべきだと思いますか?
村田課長:例えば、実需を取り扱っている会社であっても投資的な観点や知識を身につける必要があります。より専門的な知識を持ち、顧客のライフプランに合わせた提案ができるようになる必要があります。
将来的な展望について教えてください。
村田課長:私が所属している不動産開発部は、中央住宅の中でも一番新しい事業部です。新築だけでなく、中古物件の再生事業なども展開しており、ポラスが培ってきたノウハウを中古物件やリノベに取り入れることで、他にはないサービスが提供できると確信しています。
例えば、若い世帯にはまず比較的価格が安く、当社の特徴でもある空間を広く感じるスキップフロアのあるリノベの中古マンションを購入してもらう。そして住宅ローン控除などを活用してもらったあとに、物件を売却するなどして、新築戸建てに住み替えていただく。
こういった住まいの道しるべを、お客様に提案するのも面白いんじゃないかと思っています。総合的な住まいのソリューションを提供していきたいですね。
当社もそういった取り組みに役立てるようにさらにサービスを拡充していきます。
村田課長
:無人内見は、我々の働き方改革の一環として導入しましたが、結果的にお客様のニーズにも合致していて、非常に手応えを感じています。今後もさらに活用の幅を発展させていきたいですね。 ポラスの経営理念に「業界の魁となる」という言葉があります。その使命を果たすためにも、新しい取り組みにはどんどんチャレンジしていきたいですね。お客様にとっても、我々にとっても、Win-Winの関係を築ける新しいビジネスモデルを作っていく。それが私の、そしてポラスの展望です。